一、風止み
健太が縁側で宿題の絵日記を広げていたのは、もうすぐ四時になろうかという頃だった。八月の太陽はまだ高い位置にあったが、その光は妙に力がなく、世界から彩度を一枚抜き取ったように白茶けて見えた。
風が、ぴたりと止んだ。
さっきまで風鈴をちり、ちりと控えめに鳴らしていた風が、まるで呼吸を止めたかのように静まり返る。同時に、むわりと生ぬるい空気が肌にまとわりついた。土と草いきれの匂いに、微かに鉄が錆びるような匂いが混じる。祖母はそれを「夕立の知らせ」だと言った。
健太はクレヨンを置き、庭の向こうに広がる空を見上げた。西の空の、山の稜線に沿って、巨大な積乱雲が城壁のようにそそり立っている。その内側で、まるで巨大な心臓が脈打つように、鈍い光が明滅しているのが見えた。まだ音は聞こえない。
世界から音が消えたようだった。蝉の声も、遠くの国道を走る車の音も、何もかもが分厚いガラスの向こう側へ行ってしまったかのようだ。ただ、風鈴だけが、風もないのに、一度だけ「りん」と澄んだ音を立てた。まるで誰かが指で弾いたような、不自然な音だった。
二、呼ばわる声
健太は眉をひそめ、風鈴を見つめた。祖母がこしらえた、少し歪なガラスの風鈴。その下に揺れる短冊には「息災」と書かれている。その短冊が、ぴくりとも動いていない。
――夕立の前には、道に出てはいけないよ。
いつか祖母が言っていた言葉が、不意に蘇る。
――呼ばわる声がしても、返事をしてはいけない。振り返ってもいけない。
「呼ばわる声?」
健太がそう聞き返すと、祖母は皺だらけの顔で、ただ黙って首を横に振るだけだった。
その時だ。
――― おいで。
遠くで、雷が鳴った。いや、違う。それは雷鳴ではなかった。低く、長く尾を引く音。男のようでもあり、女のようでもあり、それどころか人間の声ですらないような、奇妙な響き。だが、健太にははっきりと「おいで」と聞こえた。
ぞわり、と首筋に鳥肌が立つ。
空耳だ。そうに決まってる。夕立の前は、いつもと少しだけ世界が違って見えるだけだ。健太は自分に言い聞かせ、慌てて絵日記に視線を戻した。白い画用紙の上には、描きかけの青い空と入道雲。しかし、その絵の空までもが、不吉な灰色に見えてくる。
――― こっちにおいで。
今度は、さっきよりも少しだけ近くで聞こえた。庭の向こう、鬱蒼と茂る鎮守の森の方角からだ。健太は、ぎゅっと目を閉じた。心臓が早鐘を打ち始める。
返事をしてはいけない。
振り返ってもいけない。
祖母の言葉が、頭の中で警鐘のように鳴り響く。
三、濡れた足跡
風が再び吹き始めた。今度の風は、生ぬるいだけではない。何か湿った、重いものを引きずってくるような風だった。嗅いだことのない匂いがする。甘いような、それでいて、川底の泥をかき混ぜたような、澱んだ匂い。
風鈴が、狂ったように鳴り出した。「りん、りん、りん、りん、りん!」と、誰かが必死に助けを求めるように激しく鳴り続ける。
健太は耐えきれず、顔を上げた。
見てはいけない。そう思うのに、眼が勝手に鎮守の森の方を向いてしまう。木々が、黒い影の塊となってざわめいている。その枝々の隙間に、何かが見えた気がした。
白い、何か。
ひらり、と風に舞う着物のような。
いや、違う。
くねり、と動く、節の多い指のような。
その瞬間、世界が閃光に包まれた。耳をつんざく轟音と共に、稲妻が空を引き裂き、庭のすべてを白く染め上げる。健太は思わず両手で顔を覆った。
心臓が喉から飛び出しそうだった。稲光の残像が、瞼の裏でちかちかと明滅している。
やがて、ぽつり、と大きな雨粒が健太の頬を叩いた。次いで、ぽつ、ぽつ、と。それは瞬く間に数を増し、ざああっという凄まじい音と共に、白く煙るほどの豪雨となった。
風鈴の音も、奇妙な匂いも、呼ばわる声も、すべてが夕立の轟音にかき消されていく。健太は弾かれたように立ち上がると、縁側から座敷へ転がり込み、ぴしゃりと力任せにガラス戸を閉めた。
雨は、すべてを洗い流してくれる。そう思った。
けれど、健太は気づいてしまった。ガラス戸を閉める、その刹那。雨に濡れる庭石の上に、くっきりと残っていたものに。
それは、大きな、裸足の足跡だった。
水たまりを踏んだように濡れた跡が、一つだけ。
鎮守の森から、健太がいた縁側の、すぐ手前まで。
足跡は、そこから先へは続いていなかった。まるで、そこで忽然と消えてしまったかのように。
その日を境に、健太が風鈴の音を聞くことは二度となくなった。どんなに強い風が吹いても、彼の耳には、あの澄んだ音はもう届かない。ただ、夕立が来るたびに、あの呼ばわる声と、鉄の錆びるような匂いが、記憶の底から蘇ってくるのだった。
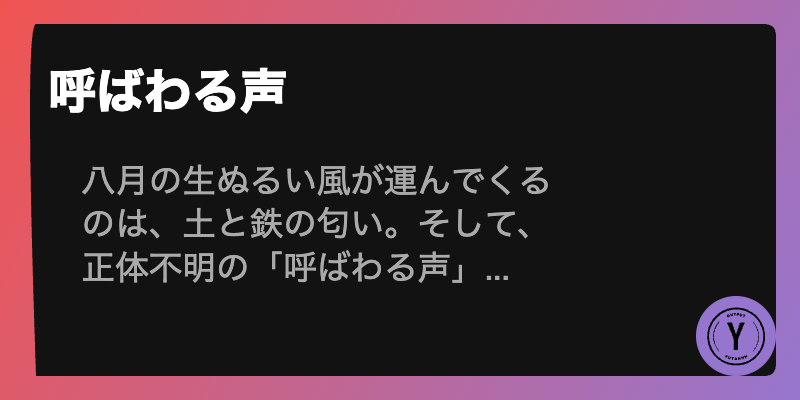
コメント