一、霧の道標
高木の運転する営業車が、本来あるべきアスファルトの感触を失ったのは、もう三十分も前のことだった。
カーナビの画面は、「GPSを測位できません」という無慈悲なメッセージを浮かべたまま、真っ暗に凍りついている。スマホの地図アプリも、広大な緑の海に自車位置を示す青い点をぽつんと表示するだけで、道一本描かれていない。もちろん、電波は圏外だ。
「……最悪だ」
思わず声が漏れた。北関東の顧客先からの帰り道、高速が事故で閉鎖されていたため、ナビの勧める「迂回路」に入ったのが間違いだった。最初は快適な国道だったはずが、いつの間にか道幅は狭まり、舗装はひび割れ、今ではほとんど砂利道に近い。ヘッドライトが照らし出すのは、両脇から迫る木々の黒い影と、濃くなっていく一方の夜霧だけだ。
ごつん、と何かが車体の下を擦る音がして、高木は舌打ちした。ガソリンの残量計の針も、もうずいぶんと左に傾いている。こんな場所で立ち往生するのだけはごめんだった。
その時、ライトの光の中に、ぼうっとした白い影が浮かび上がった。高木は身構えたが、それは道の脇に立つ、古びた石仏だった。首は欠け、顔のあたりは黒い苔に覆われている。その肩に、誰かが赤い涎掛けのようなものを結びつけていた。こんな山奥に、誰が。
石仏を通り過ぎた直後、カーラジオの音声が乱れた。ザーッという激しいノイズに混じって、何か、歌のようなものが一瞬聞こえた気がした。
―――とおりゃんせ……とおりゃんせ……
「気味が悪い……」
高木は悪態をつき、ラジオの電源を乱暴に切った。静寂が戻る。いや、完全な静寂ではない。風が木々を揺らす音、どこか遠くで獣が鳴く声、そして、車のエンジン音以外に、何か別の音が混じっている。
こつ、こつ、こつ……。
石を叩くような、乾いた音が、断続的に聞こえてくる。まるで、自分の車の後を、誰かが杖をつきながらついてくるような……。
高木はバックミラーに目をやった。濃い霧が渦巻いているだけで、何も見えない。気のせいだ。疲れているんだ。彼はそう自分に言い聞かせ、アクセルを少しだけ強く踏み込んだ。
二、河原の童子(わらべ)
坂道はますます険しくなり、エンジンが苦しげな唸りを上げ始めた。どうやら、ここが峠の頂上付近らしい。道がわずかに開け、平坦な場所に出た。
高木は、そこに広がる光景に息を呑んだ。
道の両脇に、無数の石積みが広がっている。大人の背丈ほどもあるものから、子供が積み上げたような小さなものまで、数え切れないほどの石の塔。まるで、賽の河原だ。ヘッドライトに照らされた無数の石積みが、まるで墓標のように林立している。
そして、高木は見てしまった。
石積みの影から影へと、ゆらり、と動くものを。一つではない。三つ、四つ……いや、もっといる。それは、小さな子供くらいの背丈だった。霧のせいで輪郭はぼやけているが、それが複数、蠢くように動いているのは確かだった。
先ほどの、石を叩く音。
こつ、こつ、と。
あれは、この子供たちが石を積む音だったのだ。
高木は金縛りにあったように動けなかった。恐怖で全身の血が凍りつく。あれは、生きた人間ではない。この世のものではない。理屈ではなく、本能がそう告げていた。
そのうちの一つの影が、ふいとこちらを向いた気がした。
高木は我に返り、絶叫に近い声を上げてアクセルを床まで踏み抜いた。タイヤが砂利を激しくかき鳴らし、車体が大きく揺れる。石積みの間を縫うように、車は暴走した。
どんっ!
不意に、フロントガラスに衝撃が走った。何かがぶつかったのだ。高木は悲鳴を上げ、ハンドルを切った。車はスピンし、斜面を覆う雑木林に突っ込んで、ようやく止まった。
しん、と静まり返る車内。高木は荒い息を繰り返しながら、震える手で顔を覆った。
今、ぶつかったのは。
あの影の一つだ。子供を、轢いてしまったのか?
いや、違う。あれは、子供なんかじゃない。
おそるおそる顔を上げ、フロントガラスを見る。ひび割れたガラスの向こう、ボンネットの上に、それがいた。
それは、逆さまになってこちらを覗き込んでいた。
顔があるべき場所は、のっぺりとした影になっていて、目も鼻も口もない。ただ、ぐっしょりと濡れた黒髪が、だらりと垂れ下がっている。
そして、その影が、こつ、こつ、とフロントガラスを指で叩き始めた。
―――ここは……とおれない……
ラジオを切ったはずなのに、スピーカーから直接、声が聞こえた。それは、何人もの子供の声が重なったような、奇妙な合唱だった。
―――ひとり、おいてけ……
―――ひとり、よこせ……
ガラスを叩く音が、一つ、また一つと増えていく。車の周りを、あの影たちが取り囲んでいるのだ。こつ、こつ、こつ、こつ!まるで豪雨のように、無数の指が車体を叩き続ける。
高木の理性は、そこで完全に焼き切れた。
三、連れてきたもの
意識が浮上した時、耳に入ってきたのはけたたましいクラクションの音だった。
「おい!大丈夫かあんた!」
窓の外から、大型トラックの運転手らしき男が叫んでいる。高木がぼんやりと周囲を見回すと、そこは片側一車線の、見慣れた国道だった。朝の光が眩しい。昨夜の峠道は、どこにもない。
「すみません……ちょっと、居眠りを……」
「危ねえなあ!こんな路肩で止まって!まあいいや、気ぃつけなよ!」
トラックは走り去っていく。高木はしばらく呆然としていたが、やがて昨夜の出来事が悪夢ではなかったことを悟った。
車のボンネットは、中央が大きく凹んでいた。
フロントガラスには、蜘蛛の巣状のひびが走っている。
そして、車体の至るところに、泥のついた、小さな子供の手形がびっしりと残されていた。
高木は震えながら車を発進させた。一刻も早く、この場所から離れたかった。
しばらく走り、町の明かりが見えてきて、ようやく安堵のため息をついた。
悪夢は終わった。そう思った。
何気なく、ルームミラーに目をやった、その時。
後部座席の真ん中に、誰かが座っていた。
全身ぐっしょりと濡れた、赤い涎掛けをつけた、首のない石仏が。
ラジオが、勝手に鳴った。
―――とおりゃんせ……とおりゃんせ……
高木は、もう絶叫することさえできなかった。
峠は越えたかもしれない。だが、彼は決して、一人では帰れなかったのだ。
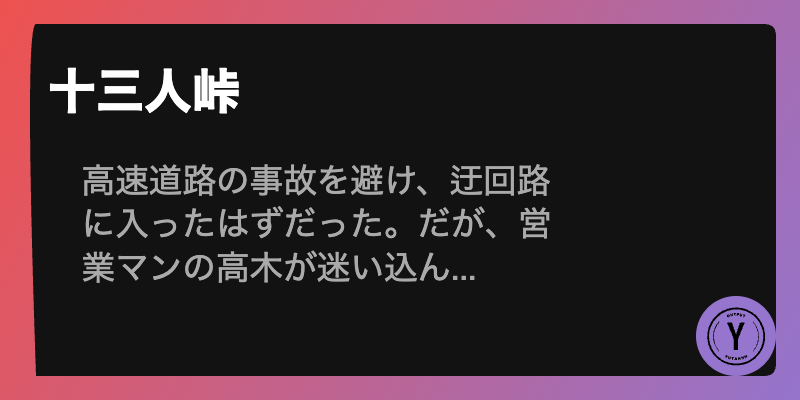
コメント