一、境界線
終電を逃した、と気づいた時にはもう遅かった。大学生のユウキは、駅の改札前でスマートフォンの画面を前に呆然と立ち尽くす。タクシー乗り場には長蛇の列。財布の中身を考えると、歩いて帰る以外の選択肢はなかった。
深夜一時過ぎ。アスファルトを叩く自分のスニーカーの音だけが、やけに大きく響く。
ユウキの脳裏に、一つの道が浮かんだ。古い霊園の脇を抜けていく、長い一本道。昼間ですら、どこか空気が違うあの道を、この時間に歩くのは正気の沙汰ではない。
だが、アルコールと疲労は、彼の正常な判断力を鈍らせていた。
「……大丈夫だろ」
誰に言うでもなく呟き、ユウキは街灯の少ない暗い路地へと足を踏み入れた。
すぐに、空気の質が変わったのが分かった。ひんやりと湿り気を帯び、濃い土と古びた線香の匂いが混じり合う独特の空気。道の左手には、高い塀がどこまでも続いている。その向こう側に何があるのか、ユウキは知っていた。そして、それを今は意識しまいと、固く心に決めていた。
視線を前に固定し、ただひたすらに歩く。自分の足音だけが、世界の全ての音だった。
風もないのに、塀の向こうで卒塔婆が「カタ」と一度だけ、乾いた音を立てた。
気のせいだ。木が擦れただけだ。ユウキは早鐘を打つ心臓を無視して歩き続ける。
道の真ん中に、ぽつんと何かが落ちていた。
黒い、丸い染みのように見える。ユウキは足を止め、目を凝らした。それは、色褪せた赤い手毬だった。
なぜ、こんな場所に。
その問いが、先ほどまで無視していた場所の持つ意味を、彼の心に引きずり出した。塀の向こう。無数の墓石。静かに眠る死者たち。
無視しよう。関わってはいけない。本能が警鐘を鳴らす。
だが、道の真ん中に転がるそれは、あまりにも場違いで、そしてひどく物悲しく見えた。おそらく、誰かが供えたものだろう。風で転がり落ちたのかもしれない。元の場所に戻してやるのが、人として正しい行いなのではないか。
ほんの数秒の葛藤の末、ユウキはゆっくりとそれに近づき、拾い上げた。
ひやりと冷たく、雨にでも濡れたようにじっとりと湿っていた。指先に、不快な感触が残る。
彼は塀の切れ目から霊園の中を覗いた。月明かりに照らされた空間に、赤い涎掛けをつけた小さな地蔵がいくつも並んでいる。彼はその一つを選び、足元にそっと手毬を置いた。これでいい。もう関わるのはやめよう。
そう心に決め、彼は再び道を歩き始めた。
二、不在の視線
何も起こらない。
背後で音がするわけでも、何かが追いかけてくるわけでもない。ただ、静寂が続いている。ユウキは、自分の過剰な警戒心を少しだけ笑った。やはり、気のせいだったのだ。
しかし、奇妙な感覚があった。
背中に、誰かの視線が突き刺さっているような。
いや、違う。視線ではない。もっと曖昧な、気配とでも言うべきもの。まるで、自分が何か大事な役割を果たし終えたのを、じっと見届けられているような、そんな落ち着かない感覚。
振り返りたい衝動に駆られるが、それを必死でこらえる。見てはいけない。一度見てしまえば、それはもう「気のせい」では済まなくなる。
彼は、ただ前だけを見て歩みを速めた。
道の終わりが見えてきた。大通りのオレンジ色の光が、まるで天国からの救いの光のように見える。あと少し。
その時、道の先の闇の中に、赤い点が一つ、ぽつんと見えた気がした。
ユウキは足を止める。
まさか。そんなはずはない。
目を凝らす。しかし、そこには何もない。街灯の光の反射か、目の錯覚だろう。
彼は再び歩き出す。
だが、あの赤い点が、網膜に焼き付いて離れない。
それは、さっき彼が拾った手毬と、同じ色をしていた。
ユウキはもう、走っていた。
背後の気配も、前方の幻も、全てを振り切るように。大通りの光の中に転がり込んだ時、彼は何度も後ろを振り返ったが、暗い路地の入り口には、ただ闇が広がっているだけだった。
三、染み
アパートに帰り着き、鍵をかけ、チェーンをしっかりとかける。シャワーを浴びて、さっき触れた手毬の湿った感触を洗い流した。ベッドに入り、無理やり目を閉じる。悪い夢だ。疲れていただけだ。
翌朝、ユウキは何事もなかったかのように目を覚ました。昨夜の出来事は、アルコールが見せた悪夢として、記憶の隅に追いやられようとしていた。
大学へ行き、友人とくだらない話をし、講義を受ける。いつも通りの一日。
あの道を通ったことすら、もう現実味がない。
夕方、自炊をしようと冷蔵庫を開けた。パックに入ったミニトマトが目に留まる。
その一つを手に取った瞬間、ユウキは凍りついた。
指先に、あの感触が蘇ったのだ。
ひやりとした冷たさ。じっとりとした湿り気。
トマトが、あの手毬になったかのような錯覚。彼は思わずトマトを床に落とした。ころん、と乾いた音を立てて、赤い球がキッチンの隅へと転がっていく。
その日からだった。
ユウキの日常に、奇妙な染みが残り続けた。
電車の窓に映る、自分の隣の空席に、ふと赤い服を着た子供の姿を見た気がする。
雑踏の中で、ボールをつくような音が聞こえた気がして振り返るが、誰もいない。
眠りにつこうとすると、暗闇の中、部屋の隅に赤い手毬が置いてあるような気がして、何度も電気をつける。
何かがいるわけではない。追いかけてくるわけでもない。
ただ、あの夜、ほんの少しの善意から境界線を越えてしまったことで、彼の世界には、決して消すことのできない「残響」が、いつまでも、いつまでも、鳴り響いている。
彼の日常そのものが、静かに、墓場の隣になってしまったのだ。
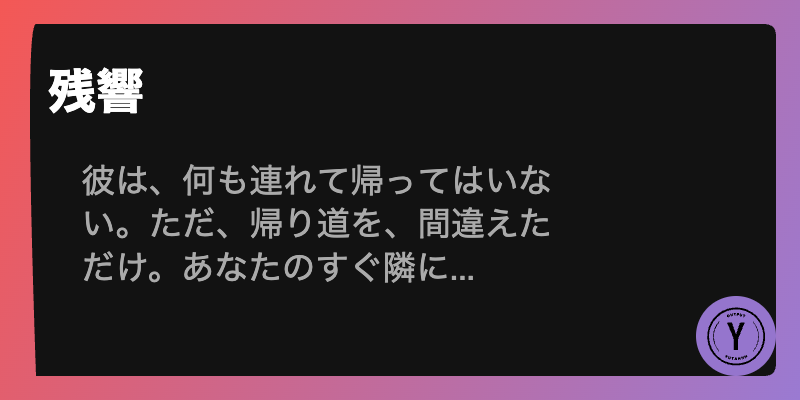
コメント