一、静寂のひび割れ
東京という街は、音で出来ていた。
電車の絶え間ない走行音。遠くで鳴り響くサイレン。雑踏のざわめき。アパートの隣室から漏れるテレビの音声。それら無数の音が混ざり合い、一つの巨大な環境音となって、街全体を分厚く包み込んでいる。
相田祐樹は、上京して一ヶ月、その事実を全身で理解していた。地方都市の閑静な住宅街で育った彼にとって、東京の「無音」とは、音が何一つない状態のことではなかった。一つの音が、他の全ての音を飲み込んだ瞬間に訪れる、相対的な静寂。それが、この街の静けさだった。
彼が住むことになった「月見荘」は、そんな東京の音の生態系から、奇跡的に取り残されたような場所だった。私鉄沿線の駅から徒歩十五分。商店街の喧騒が嘘のように途切れた先に、その二階建ての木造アパートはひっそりと佇んでいた。昭和の面影、と言えば聞こえはいい。要は、安普請の古いアパートだ。親からの仕送りを頼りに暮らす貧乏学生にとって、選択の余地はなかった。
相田の部屋は二階の角部屋、二〇一号室。六畳一間の、日当たりの悪い和室。壁は薄く、隣の二〇二号室の住人がいつ帰ってきて、いつトイレに立ったかまで、生活音で何となく分かった。だが、それも最初の数日のこと。隣人は昼夜逆転の生活なのか、あるいは長期の不在なのか、ここ数週間、その気配を感じることはほとんどなかった。おかげで、部屋は気味が悪いくらいに静かだった。
最初の異変は、五月の連休が明けた頃に訪れた。
深夜。レポート作成に行き詰まり、コンビニで買った缶コーヒーを啜っていた時だった。
コン。
不意に、音がした。
二〇二号室とを隔てる、壁の向こうから。
木を、硬い何かで軽く叩くような、乾いた音。一つだけ鳴って、すぐに消えた。相田は耳を澄ませたが、続きはない。
(……気のせいか)
家鳴りだろう。このアパートは古い。夜中に柱や壁が軋む音は、もう聞き慣れていた。彼はそう結論づけ、再びパソコンの画面に向かった。
だが、翌日の夜。
同じ時刻。昨日と全く同じ、寸分の狂いもないタイミングで、それは再び鳴った。
コン。
今度は、聞き間違いようがなかった。
短く、乾いた、意志のある音。
家鳴りのような、不規則で偶発的な響きではない。誰かが、何かを、壁に一度だけ、ぶつけている。
なんだ?
隣人は帰ってきていたのか。だとしても、一体何をしているというのか。壁に釘でも打っている? 深夜二時に? 一発だけ?
疑問は浮かんだが、それ以上追及する気にはなれなかった。都会の集合住宅では、隣人の不可解な行動にいちいち首を突っ込むべきではない。そういう処世術を、彼はこの一ヶ月で学びつつあった。
しかし、その音は、三日目も、四日目も、全く同じ時刻に繰り返された。
深夜二時きっかりに、一度だけ、「コン」と。
まるで、時計の時報だった。あるいは、何かの合図。
その規則性が、相田の神経を少しずつ逆撫でていった。一度意識してしまうと、もう駄目だった。深夜一時を過ぎる頃から、彼は自然と壁を意識するようになった。固唾を飲んで、その瞬間を待ってしまう自分がいた。
そして、二時。
コン。
音がすると、彼は安堵する。ああ、今日も鳴った、と。
同時に、言い知れぬ不気味さに全身が粟立った。なぜ、安堵などしている?
まるで、その音を聞くことが、毎夜の儀式の一部に組み込まれてしまったかのようだった。
その日、相田は一つの実験を試みた。
深夜一時五十九分。彼はスマートフォンのアラームを、二時に鳴るようにセットした。電子的なアラーム音で、あの「コン」という生々しい音の記憶を上書きしてしまおうと思ったのだ。
やがて、その時が来る。壁の向こうに意識を集中させる。
心臓が、嫌な音を立てる。
——そして。
ピピピッ、ピピピッ。
けたたましい電子音が、部屋の静寂を破った。相田は慌ててそれを止める。
静けさが戻る。
彼は、壁の向こうに耳を澄ませた。
一分、経った。
二分、経った。
……鳴らない。
今夜は、あの音は鳴らなかった。
(そうか、たまたまだったのか)
やはり、何か意味があったわけではない。これまで続いていたのが、偶然だったのだ。馬鹿馬鹿しい。くだらないことで、勝手に神経をすり減らしていた。
相田は大きく息を吐き、ベッドに潜り込んだ。安堵からか、体が一気に重くなる。
このまま、深く眠れそうだ。
意識が遠のき始めた、その時だった。
コン。
壁の向こうから、はっきりと聞こえた。
時刻は、二時三分。
いつもより、三分遅れて。
まるで、こちらのアラームが終わるのを、待っていたかのように。
ぞわり、と。背筋に冷たいものが走った。
偶然?
本当に、これは偶然なのか?
相田は暗闇の中、じっと壁を見つめた。薄いベニヤ板一枚の向こうにいる「何か」が、こちらの行動を全て把握している。そんな、ありえない妄想が、脳裏を掠めて離れなかった。
二、壁の向こう側
あの日を境に、相田の世界から「偶然」という言葉の意味が剥奪された。
壁の向こうの「何か」は、明らかにこちらの状況を認識している。それはもはや疑いようのない事実だった。
深夜二時の定点観測は、より悪質なものへと変貌を遂げた。
「コン」という音は、もはや時報ではない。相田の行動に対する「返信」になった。
彼がベッドで寝返りを打つ。——コン。
彼が咳払いをする。——コン。
教科書のページをめくる乾いた音。鼻をすする音。スマホをタップする微かな音。その全てに、「何か」は壁を叩く音で応答した。一つ一つの行動を採点するかのように、あるいは、その存在を執拗に主張するかのように。
それは、監視されているという恐怖を通り越し、まるで巨大な獣に弄ばれているような、絶対的な無力感を相田に与えた。こちらの全ての行動は筒抜け。それなのに、相手の姿も、目的も、正体も、何も分からない。薄い壁一枚が、世界を完全に隔てていた。
不眠の日々が続いた。
隈が深くなり、授業に集中できず、友人の言葉もどこか遠くに聞こえる。世界が、薄い膜を隔てた向こう側の出来事のように感じられた。このままでは駄目になる。意を決した相田は、アパート一階の大家の部屋を訪ねた。
呼び鈴を鳴らすと、ギ、と油の切れた音を立ててドアが開き、皺くちゃの顔が覗いた。月見荘の大家の老婆だ。いつも黒い着物を着て、陽の光を避けるように暮らしている。
「……二〇一号室の」
「あの、隣の二〇二号室のことで、ちょっと……」
相田が言いかけると、老婆の目の色が、ほんの少しだけ鋭くなった。
「夜中に、物音がうるさくて。何か、壁を叩くような……」
「……」
老婆は答えなかった。ただ、爬虫類のような、瞬きの少ない目つきで相田の顔をじっと見つめている。その沈黙が、肯定よりも雄弁に異常を物語っていた。
「何か、ご存知ないですか。どんな方が住んでるんでしょうか」
食い下がる相田に、老婆は不意に、乾いた唇を開いた。
「あんた」
その声は、ひどく嗄れていた。
「壁に、耳なんか当ててないだろうね」
「え……」
「あの部屋はね……」
老婆は何かを言いかけたが、ふと口をつぐみ、首を横に振った。
「……いや、なんでもない。とにかく、関わっちゃいけないよ。いいね。隣のことは、忘れな」
それだけ言うと、老婆は一方的に話を打ち切り、ゆっくりとドアを閉めた。取り付く島もない。だが、相田の背筋は凍りついていた。
あの忠告。それは、隣人の出す騒音に悩む店子への対応ではなかった。まるで、猛獣の檻に近づく子供を諭すような、切実な響きがそこにはあった。
自室に戻り、改めて問題の壁と対峙する。
ベニヤ板に、安っぽい木目調の壁紙が貼られているだけ。何の変哲もない、アパートの壁だ。
だが、よく見ると、壁紙の木目の模様が、ある種のパターンを形成しているように見えた。気のせいだろうか。以前からこうだっただろうか。
人の顔。
そうだ、人の顔に見える。
無数の木目が絡み合い、一つの巨大な顔を形作っている。苦悶に歪んだ口。固く閉じられた目。それは、相田が鏡で見る、自分自身の憔悴しきった顔にもどこか似ていた。
彼は後ずさった。おかしくなっている。不眠で、神経が過敏になっているだけだ。壁紙の模様が顔に見えるなんて、典型的なパレイドリア現象じゃないか。そう頭では分かっているのに、一度「顔」だと認識してしまった脳は、もうそれをただの「木目」に戻すことができなかった。
その日から、相田は壁の「顔」を監視し始めた。「何か」が自分を監視しているように、「顔」を監視することで、精神の均衡を保とうとしたのかもしれない。
そして、金曜の夜。
大学の友人である佐藤が、課題の相談だと言って部屋を訪ねてきた。他人と話すのは久しぶりだった。相田は少しだけ安堵し、佐藤を部屋に上げた。
「お前、なんか窶れたな。ちゃんと食ってんのか?」
「まあ、それなりに」
当たり障りのない会話を交わす。佐藤がいる間は、不思議と壁の音はしなかった。「何か」も、来客がいることは分かっているのだろうか。
話が一段落したとき、相田は思い切って切り出した。
「なあ、佐藤。ちょっと、見てもらいたいものがあるんだけど」
「ん? なんだよ」
「あの壁なんだけどさ。模様が、人の顔に見えないか?」
佐藤は怪訝な顔で壁に視線をやった。数秒、首を傾げた後、彼はあっけらかんと言った。
「顔? ……いや、ただの木目だろ。どこが?」
「いや、ほら、あそこが目で、ここが口で……」
相田が必死に指差して説明しても、佐藤は「全然わかんねえよ。お前、疲れてんじゃねえの」と笑うだけだった。
その時だった。
コン。
壁から、小さな音がした。
「今の音、聞こえたか!?」
相田は叫んだ。佐藤はきょとんとしている。
「音? 何も聞こえなかったけど」
「嘘だろ! 今、確かに鳴ったんだ! コンって!」
「いや、だから何も……。おい、相田、お前、本当におかしいぞ」
佐藤の目が、心配から侮蔑のそれに変わっていくのが分かった。狂人を見る目。哀れなものを見る目。
相田は、全身の血が急速に冷えていくのを感じた。
聞こえないのか。
見えないのか。
俺にだけ?
なぜ?
佐藤は居心地が悪そうに、そそくさと帰っていった。一人残された部屋は、再び墓場のような静寂に包まれる。
違う。静寂じゃない。
壁の向こうで、「何か」が息を潜めている。そして、嘲笑っている。
相田は、ゆっくりと壁に視線を戻した。
さっきまで、固く閉じられていたはずの「顔」の瞼が。
ほんの少しだけ、開いているように見えた。
染み込む記憶
孤立は、恐怖を熟成させる最高の培養液だった。
佐藤との一件以来、相田は誰にも相談できなくなった。大学へは行ったが、誰とも目を合わせず、講義が終わるとすぐにアパートへ逃げ帰る。友人を失い、日常が剥がれ落ちていく。彼の世界は、六畳一間のこの部屋だけになった。
そして、その世界の全てである部屋は、もはや彼の味方ではなかった。
壁の「顔」は、日に日に鮮明になっていく。それはもはや、ただの模様ではない。相田の感情を映す鏡だった。彼が絶望すれば眉間に皺を寄せ、恐怖に震えれば口元を歪めて笑う。壁は生き、彼を観察し、弄んでいた。
音の模倣は、さらに悪質になった。
ある夜、相田が故郷の母親と電話で話していた時のことだ。他愛のない世間話。その最中、壁が「コン、コン、コン」と不規則に鳴り始めた。最初は気にしないように努めたが、彼は気づいてしまった。そのリズムは、不器用なモールス信号のように、母親が話す言葉の長短をなぞっている。
『体にだけは気をつけるのよ』
コン、コン、コンコン、コン、コンコンコン。
電話を切った後も、音は止まない。今度は、相田が考えていることを読み取り、返事をするかのように鳴り始めた。
(うるさい、黙れ)
コン。コンコンコン。
(やめてくれ……!)
コン、コン、コンコンコンコン、コンコン。
思考が筒抜けになっている。脳に直接、不快な音が響くようだった。彼は耳を塞いだが、音は頭蓋の内側から聞こえてくる。壁と自分の境界が、曖昧になっていく感覚。部屋そのものに、精神が溶かされていくような恐怖。
このままでは発狂する。
相田は最後の理性を振り絞り、敵の正体を探るべく行動を開始した。大家の老婆が何かを隠している以上、このアパートには何かがあるはずだ。彼は駅前の図書館へ向かい、郷土資料の棚を漁った。古い住宅地図、地域の会報、そして過去の新聞の縮刷版。
何時間もかけてページをめくり続け、彼はついに一つの記事を見つけ出した。
三十年前の、地方紙の小さな三面記事。
『アパートで男性の白骨遺体発見』
月見荘、二〇一号室。まさに、今自分が住んでいるこの部屋で、当時二十代の男性が死んでいた。死後、数年が経過しており、死因は不明。ただ、記事の最後には、こう締めくくられていた。
『室内の壁には、無数の引っ掻き傷が残されており、警察では事件性の有無も含め慎重に捜査している』
心臓が凍った。
三十年前の男。この部屋で、同じように孤独に死んでいった男。壁の音も、顔も、全てはこの男の地縛霊の仕業なのだ。助けを求めて、あるいは、次の住人を道連れにするために、壁の中から合図を送っているのだ。
相田はそう確信した。
恐怖に変わりはなかったが、正体不明の「何か」に怯えるよりは遥かにましだった。敵は地縛霊。正体が分かれば、対処法もあるはずだ。彼は震える手で記事をコピーし、図書館を後にした。その背中に、司書の訝しげな視線が突き刺さっていたことに、彼は気づかなかった。
三、二〇一号室
敵の正体を「地縛霊」だと誤認したことで、相田の心には、皮肉にも闘志が生まれた。彼はインターネットで除霊の方法を調べ、近所の神社で一番強力だという御札を買い、コンビニで粗塩を仕入れた。
「出ていけ!」
彼は叫びながら、壁の「顔」の中心に、御札を叩きつけるように貼った。そして、部屋の四隅に塩を撒く。これで、少なくとも今夜は安眠できるはずだ。
だが、儀式は嘲笑された。
深夜二時。御札はひとりでに、するりと壁を滑り落ちた。そして、畳に落ちた瞬間、まるでマグネシウムを焚いたように、ぼっ、と青白い炎を上げて燃え尽きた。撒いた塩は、じゅう、と音を立てて黒く変色し、床に染みをつくる。
壁の「顔」が、これまでで最も醜悪に歪んだ。
それは、勝利を確信した者の、侮蔑に満ちた笑みだった。
相田は悟った。生半可な儀式など、この化け物には通用しない。それどころか、怒りを買っただけだ。
音が鳴り始める。
コン、コン、コン、コン、コン……!
これまでの、単発の音ではない。マシンガンのような、狂った連打。部屋全体が振動し、壁紙がびりびりと裂けていく。壁が、呼吸するように、膨張と収縮を繰り返している。
もう、駄目だ。
殺される。
相田の精神の糸は、ついに焼き切れた。彼は押入れから、引っ越しの時に使った金槌を掴み出した。
「うるさい! うるさい、うるさいうるさいうるさい!」
半狂乱で叫びながら、彼は壁の「顔」の中心、嘲笑う口の部分に、金槌を振り下ろした。
ゴッ!
鈍い音が響き、壁紙が破れ、ベニヤ板が砕け散る。
やったか?
相田は、息を切らしながら、自分が開けた穴を覗き込んだ。
その向こうにあったのは、隣室の壁ではなかった。コンクリートの壁でも、断熱材でもなかった。
そこは、ぬるりとした、暗く湿った肉塊のような「何か」で満たされていた。
そして、その蠢く肉の中から、無数の人の顔のようなものが、ぶくぶくと浮かび上がってきた。老若男女、様々な顔。みな、苦悶の表情で口を開き、声にならない叫びを上げている。三十年前に死んだ青年らしき顔も、その中にあった。
壁は、隣室との境界などではなかった。
それ自体が、人を喰らい、取り込み、コレクションする、巨大な生物だったのだ。
肉塊の中から、何本もの腕が伸びてくる。相田の腕を、足を、髪を掴もうとする。
「あ……ああ……ああああああああああああああ!」
目の前の、現実とは思えない光景。相田の理解力は限界を超え、彼の意識は、ぷつりと糸が切れるように途切れた。
次に目を覚ました時、彼は自室の布団の上に寝ていた。
窓から差し込む朝日が、やけに目に眩しい。
相田は、恐る恐る体を起こした。
……静かだ。
あの、狂ったような打撃音は聞こえない。
彼は、ゆっくりと壁に視線を向けた。
穴は、ない。
壁紙はどこも破れておらず、そこにあるのはただの木目の模様だけだった。人の顔など、どこにも見えなかった。
全て、夢だったのか。
不眠と栄養失調とストレスが見せた、長くて、ひどくリアルな悪夢。
そう、思うしかなかった。
だが、もうこの部屋には一秒もいたくない。悪夢の舞台だった場所に、住み続けられるはずがない。相田は、その日のうちに大学に休学届を出し、震える手で不動産屋に電話をかけた。違約金を払い、彼は逃げるように月見荘を後にした。
一週間後。
相田は、新しいアパートにいた。月見荘からは電車で一時間ほど離れた、コンクリート造の近代的なマンションだ。壁も厚く、隣の生活音は全く聞こえない。
彼は、まだ段ボールに囲まれた部屋の真ん中で、大きく息を吸い、そして吐いた。
ようやく、日常が戻ってきた。
あの悪夢のような日々は、終わったのだ。
彼は安堵のため息をつき、月見荘から持ってきた最後の段ボール箱を開けた。中には、大学の教科書や、着替えの類が詰め込まれている。
その荷物を一つ一つ取り出していた、その時だった。
コン。
微かな、しかし聞き間違いようのない音がした。
相田の動きが、凍りつく。
音源は、どこだ?
耳を澄ます。心臓が、またあの嫌な音を立て始める。
彼は、ゆっくりと音のした方へ顔を向けた。
それは、今まさに彼が手をかけていた、段ボール箱の中からだった。
教科書の間に挟まっていた、彼自身の右手。その人差し指の爪が、硬い表紙を、無意識に、一度だけ叩いていた。
コン。
恐怖は、部屋に憑いていたのではない。
『二〇一号室』は、相田祐樹という、新しい「部屋」を見つけたのだ。
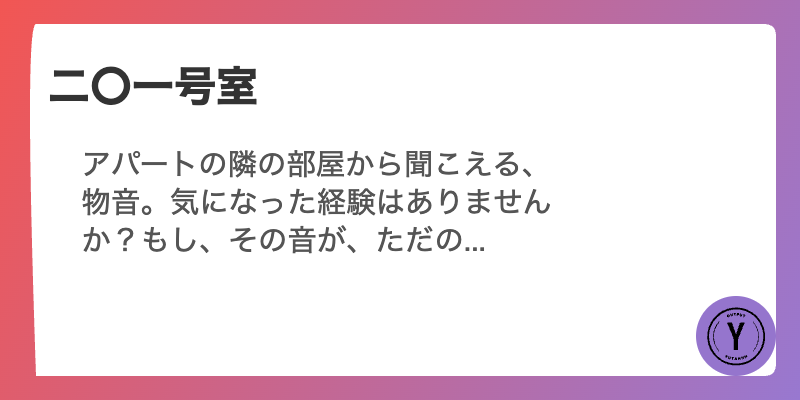
コメント