一、帰郷
東京の空は、灰色だった。
ホームに滑り込んできた新幹線の金属音さえ、湿った空気に吸い込まれて鈍く響く。人々の早足、無関心な視線、鳴り響くスマホの通知音。そのすべてから逃げ出したかった。
目的地の駅に降り立った途端、むわりとした緑の匂いと、肌にまとわりつくような熱気が身体を包んだ。肺が、久しぶりの濃い空気で満たされる。空はどこまでも青く、蝉時雨が容赦なく降り注いでいた。水守町。私の故郷。
「葉月、よう帰ってきたねぇ」
改札の前で、祖母が皺くちゃの笑顔で手を振っていた。その小さな背中を追い、実家までの道を歩く。記憶の中よりも、道は狭く、舗装はひび割れていた。すれ違う老人たちが、じろり、と私を見る。すぐに目を逸らすが、その一瞬の視線が、値踏みをするように冷たいのを気のせいだと思った。
祖母の家は、変わらなかった。
黒光りする廊下。風が通るたびに鳴る、ガラス戸のかすかな音。そして、線香と、古い木の匂い。畳の部屋に大の字になると、ささくれがちくりと肌を刺した。その痛みさえ、懐かしい。
夜。蛙の大合唱が聞こえる。
夕食の後、一人で縁側に座って冷たい茶を飲んでいた。その時だ。ズボンのポケットに入れていたスマートフォンが、ぶるぶると震えた。
画面に浮かび上がる「非通知設定」。
東京の喧騒の中では無視していた番号。しかし、この静寂の中では、その無機質な文字がやけに大きく見えた。なんとなく、応答ボタンを押す。
「……もしもし?」
返事はない。
ただ、――ざあぁぁ……。
マイクの向こうから聞こえるのは、ノイズ混じりの水の音。まるで、すぐそばで激しい川が流れているような。
気味が悪くなって、すぐに通話を切った。東京の誰かの、間違い電話だろう。そう思うことにした。
だが、その夜からだった。
非通知の電話は、毎日必ず、同じ時刻にかかってくるようになった。
二、波紋
帰省して三日目の昼下がり、幼馴染の圭介にばったり会った。町役場で働いているという彼は、昔の面影を残したまま、人の良さそうな青年に成長していた。
「葉月じゃん! 久しぶり。いつ帰ってきたんだ?」
「三日前にね。圭介こそ、元気そうで」
「まあな。こんな何にもないとこだけど、ゆっくりしてけよ」
圭介は笑った。その笑顔に少しだけ救われる。町の人々の視線が気になっていることを、それとなく話してみた。
「ああ、気にすんなよ。よそから人が来るのが珍しいだけだから」
そう言う彼の目が、一瞬だけ泳いだのを、私は見逃さなかった。
その日の夜も、非通知の電話は来た。
今度は出てやらない。そう決めて放置した。留守番電話に切り替わる。メッセージが一件。再生する。
「……ざあぁぁ……ちり、……」
水の音に混じって、微かな音が聞こえた。
金属が擦れるような、小さく、乾いた音。
鈴だ。
幼い頃、神社の祭りで見た神楽の鈴の音に似ていた。
翌日、祖母に電話のことを尋ねた。
「なあに、気のせいだよ。この町は電波も悪いからのぅ」
祖母はそう言って、皺の刻まれた手で私の頭を撫でた。その手が、氷のように冷たかった。
誰もが何かを隠している。
私だけが、何も知らない。
この町は、私の知っている故郷ではない。じっとりとした恐怖が、蝉の声に混じって、私の日常に波紋を広げ始めていた。
三、禍ツ瀬(まがつせ)
いてもたってもいられなくなり、町の外れにある小さな郷土資料館へ向かった。埃と黴の匂いがする、無人の建物。 [cite: 11] 受付のノートに名前を書く手も、汗で湿っていた。
書庫の奥で見つけた、分厚い町の歴史書。その中に「水守町縁起」という章があった。
ページをめくる指が、震える。
そこに、答えはあった。
――日照り続く夏、禍ツ瀬より現れし水呼び様に、清き乙女を贄として捧ぐ。贄に選ばれし者には、水呼びの鈴の音が聞こえるという……。
水呼び様。贄。鈴の音。
点と点が線になり、私の喉を締め上げた。この儀式は、百年以上前に廃れたと書かれていたが、本当だろうか。まさか。
資料館を飛び出し、圭介の元へ走った。町役場の古びた建物。すがるような思いで、彼に全てを話した。歴史書のこと、非通知電話のこと、鈴の音のこと。
圭介は、私の話を黙って聞いていた。そして、青い顔で、固く拳を握りしめた。
「……なんてことだ。そんな馬鹿げた風習が、まだ……」
彼は私の肩を強く掴んだ。
「葉月、信じてくれ。俺は、お前の味方だ。絶対に、こんなことから助けてやる」
その言葉は、暗闇の中で見つけた、たった一つの懐中電灯の光だった。
「今夜、町民は公民館で集会がある。その隙に、ここから逃げるんだ。俺が裏山を抜ける道を案内する。夜11時に、家の裏手で待っててくれ」
頷くことしかできなかった。
涙が溢れた。よかった。私は、一人じゃなかった。
四、水呼び
夜11時。
言われた通り、家の裏の木戸で息を殺して待っていると、圭介が駆けつけてくれた。
「行くぞ、葉月」
彼が私の手を引く。私たちは闇の中を走り出した。
[cite_start]草いきれがむせ返るような裏山。月明かりだけが頼りだ。木の枝が頬を掠め、鋭い痛みが走る。 [cite: 8] 息が切れ、心臓が破れそうだった。それでも、繋がれた圭介の手の温かさだけが、私を正気に保っていた。
どれくらい走っただろうか。
不意に、視界が開けた。
そこは、川に面した古い社だった。
そして、社の前には、松明の赤い光が揺らめいていた。
「……え?」
松明の明かりに照らし出されたのは、祖母をはじめとする、町民たちの顔。顔。顔。
全員が、無表情で、こちらをじっと見ていた。
「圭介……これ、どういうこと……?」
繋がれた手に、力がこもる。
圭介は、私の顔を見て、悲しそうに、本当に悲しそうに、少しだけ笑った。
「ごめんな、葉月」
「……え……?」
「これで、町が助かるんだ」
その瞬間、ズボンのポケットで、スマートフォンが最後の着信を告げた。
だが、もう電話の音は耳に入らなかった。
なぜなら、本物の鈴の音が、すぐそこで、鳴ったからだ。
ちりり、と。
圭介の背後、闇に染まった社の中から、ゆっくりと姿を現した何か。その手に握られた、古びた神楽鈴が、高く、高く、鳴り響いていた。
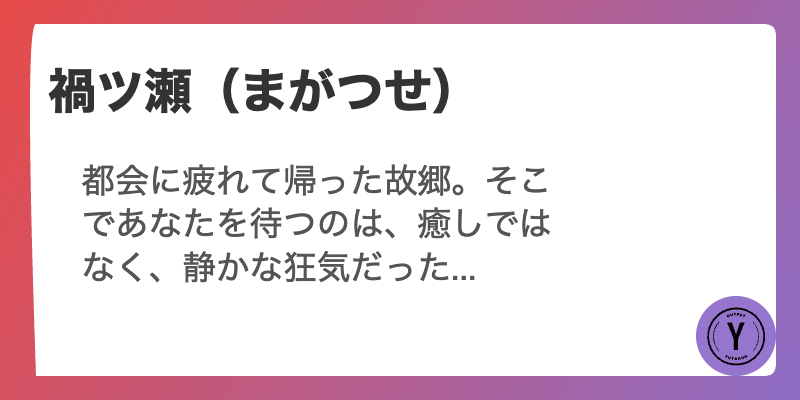
コメント