罪の残響
三澄響也(みすみ きょうや)が消えた。
その報せは、梅雨時のじっとりとした空気の中、一本の電話によってもたらされた。受話器の向こうで聞こえる響也の母親のしゃくりあげる声が、やけに遠い。俺、高槻彰人(たかつき あきと)は、気の利いた言葉一つ返せなかった。ただ、「そうですか」と呟く。それだけ。
響也とはもう何年も会っていなかった。大学を卒業してすぐ、あの事件を境に、俺たちは互いを避けるように生き始めた。
警察からの呼び出しを受け、響也の部屋に残されたものを見せられる。雑然としたワンルーム。壁一面に貼られた、日本各地の廃墟や心霊スポットの記事。その中に、一枚だけ異質なメモがあった。走り書きの文字。
『霧ヶ峰駅で待つ』
霧ヶ峰駅。
その名を見た瞬間、忘れたはずの記憶が、胃の底からせり上がってくる。腐葉土の匂い。鳴りやまない蜩(ひぐらし)の声。そして、錆びた鉄の味。
「彼が何か悩んでいた様子は?」
刑事が尋ねる。俺は首を横に振った。嘘だ。俺は知っている。響也は悩んでいた。俺と同じ罪の意識に。そして、その罪が生まれた場所が、霧ヶ峰駅だった。
部屋を出て、蒸し暑いアスファルトの上に立つ。このまま日常に戻ることは、もう許されない。響也を連れ戻さなければ。それが、あの日の罪に対する、唯一の贖罪。
俺は車のキーを強く握りしめた。行き先は、決まっていた。
霧のホーム
カーナビの地図から道が消え、鬱蒼と茂る木々の間を縫うように、車は進む。ワイパーが、濃霧を払っても払っても、視界は白く塗りつぶされていく。じっとりとした湿気が肌にまとわりつく。窓を開けると、記憶と同じ腐葉土の匂いがした。
やがて、車は行き止まりの広場に出た。その奥に、それはあった。
霧の中から、亡霊のように浮かび上がる、古びた駅舎。
「霧ヶ峰駅」
錆びついた駅名看板が、かろうじて読める。ぎしり、と音を立てる木製のドアを押し開ける。待合室には誰の姿もない。ただ、時間が止まっていた。壁の時計は五時で止まり、窓ガラスにはびっしりと埃が積もっている。
ホームに出る。ぽつんと、古びた木製のベンチが一つ。
線路があったはずの場所は、背の高い草に覆われている。廃線になって久しい。列車など、来るはずがない。
なのに。
俺はベンチに腰を下ろし、ただ待った。何を待つでもない。響也のメモには、時間が書かれていなかった。だが、何故か分かっていた。それが訪れるのは、夜だ。世界の境界線が、最も曖昧になる時間。
しん、と静まり返る。聞こえるのは、自分の心臓の音だけ。
時折、風が木々を揺らす音が、人の囁き声のように聞こえて、ぞわりと背筋を撫でた。見られている。霧の向こう側から、得体のしれない何かに。
何時間が経っただろうか。腕時計のデジタル表示が、0:00に変わった。
その瞬間。
ちりん。
遠くで、鈴の音がした。
そして、霧の奥。草に埋もれたはずの線路の先が、ぼうっと淡いオレンジ色に染まった。
幻聴ではない。甲高い警笛の音。二つのヘッドライトが、ゆっくりとこちらへ近づいてくる。
終着なき旅
ありえない。
そう思うのに、足は動かなかった。錆びたレールの上を、列車は信じられないほど滑らかに滑り込んでくる。古い、一両だけの車両。薄汚れた窓。
ぷしゅー、という音と共に、目の前でドアが開いた。
誘われるように、一歩、足を踏み入れる。
車内は薄暗かった。古めかしい赤いベルベットの座席が並んでいる。乗客はいない。ただ一人、窓際の席に座る人影を除いては。
その男が、ゆっくりとこちらを向く。
「……あきと」
掠れた声。響也だった。
頬はこけ、目の下には深い隈が刻まれている。生気のない、虚ろな瞳。
俺は駆け寄り、その肩を掴んだ。
「響也! 無事だったのか!」
響也は、俺の顔を見て、子供のように一瞬だけ表情を緩ませた。
「……ごめん」
「何がだ。帰るぞ」
「ごめんな、彰人」
響也は首を横に振った。そして、震える指で窓の外を指さす。
「もう、一人じゃ無理なんだ」
言われるままに、窓の外を見た。
そこにあったのは、見知らぬ景色ではなかった。深い森。夏の強い日差し。そして、ガードレールのない崖下の道で、血を流して倒れている、見知らぬ中年の男。その傍らで、呆然と立ち尽くす、十代の頃の俺と、響也。
俺たちが犯した、罪の光景。
「ずっと、これなんだ」
響也が呟く。
「毎日、毎時間。ずっと、この景色が流れてる。俺が、お前を庇って、嘘をついた、あの瞬間が」
列車が、ごとん、と大きく揺れた。今までよりも力強く、走り始めた気がした。
そうだ。この列車は、乗客の「後悔」を燃料にして走る。そして、俺という新たな乗客を得て、さらに勢いを増したのだ。
俺はドアに駆け寄った。だが、びくともしない。
響也が、静かに俺の隣に立った。その顔には、安堵と狂気が混じった、薄気味悪い笑みが浮かんでいた。
「彰人が次に呼ばれるって、分かったんだ。だから、俺が先に来た。お前を守りたかった」
彼の瞳から、一筋の涙がこぼれる。
「でも、駄目だった。一人じゃ、耐えられなかった。なあ、彰人。お前も、後悔してるだろ? 俺と一緒に、ここで罪を償おう。そしたら、俺たちは、ずっと一緒だ」
失踪は、俺を救うための自己犠牲。
そして、俺をこの地獄へ引きずり込むための、周到な罠。
救済者であり、断罪者。
ああ、そうか。
響也は、俺に許してほしかったのだ。そして、俺もまた、響也に許しを乞いたかった。
俺たちは、互いを求めるあまり、互いをこの終着なき牢獄に繋ぎとめてしまった。
窓の外では、若い俺が、震える声で警察に嘘の証言をしている。
あの日の光景が、また始まった。
これから、永遠に。
この、終着なき旅は、続いていく。
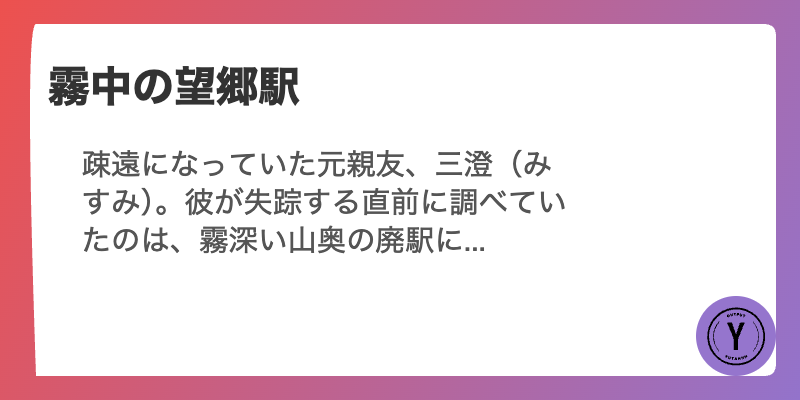
コメント