冷めたコンソメ
ちりん、と古びたドアベルが乾いた音を立てた。
店内は、外の世界から切り離されたような琥珀色の静寂に満ちていた。磨き上げられたカウンターの向こうで、白いシャツを着たマスターが、入ってきた男──工藤亮介に静かに会釈した。客は亮介一人。彼は逃げるように一番奥の革張りの椅子に身を沈めた。
「ブレンドを」
「かしこまりました」
サイフォンがくぽ、と音を立てる。その微かな音だけが、この空間が生きていることを示していた。亮介はすぐには本題を切り出せなかった。ただ、目の前の男の無駄のない所作と、客に媚びるでもなく、突き放すでもない、硝子のような視線を観察していた。ここなら、あるいは。
「……記憶を、売りたい」
カップを置く音は、しなかった。マスターは表情を変えぬまま、亮介の言葉をただ受け止めていた。
「ほう」
その短い相槌だけが返ってきた。
「価値があるかは、分からん」
亮介はカップに口をつけた。香りの飛んだ、ぬるいコンソメスープのような味がした。
「ただ、俺にはもう重い。それだけだ」
マスターは何も問わず、ただ静かにカップを拭き始めた。キュ、キュ、と布がグラスを擦る音だけが響く。その沈黙が、亮介には「それで?」と問いかけているように感じられた。急かすでもなく、探るでもない、ただそこにある沈黙。やがて、それに耐えきれなくなったように、亮介の方から重い口を開いた。
「……あれは、三十年以上も前の話だ」
栄光と裏切りのアメリケーヌソース
亮介は目を閉じた。
瞼の裏に蘇るのは、見慣れた店の厨房ではない。だだっ広いホテルのホールに特設された、いくつも並ぶ調理台の一つ。国内で最も権威ある料理コンクールの決勝会場だ。他のシェフたちの張り詰めた横顔と、金属が触れ合う神経質な音だけが響いていた。
「亮介、大丈夫か」
隣で、相棒の坂上誠人が小さな声で呟いた。無理もない。この舞台で、亮介がやろうとしていることは、セオリーから大きく外れていた。
「……まあ、見てろよ」
亮介は短く応えた。口元には、自分でも傲慢だと思うほどの笑みが浮かんでいた。
決勝の課題は「スフレ」。古典的だが、ごまかしが効かない。亮介は即興で組み立てを変えた。オマール海老の殻から取った濃厚なアメリケーヌソース。それをメレンゲと合わせ、ふっくらと焼き上げる、塩気のあるスフレ。誠人は「冒険すぎる」と最後まで言ったが、亮介の耳には届いていなかった。
やがて、審査の時が来た。
オーブンから取り出されたスフレは、夕焼け色に輝き、テーブルに置かれた瞬間に、香ばしい甲殻類の香りを放った。審査員たちの眉が、わずかに上がる。スプーンを入れた一人が、その断面を見て小さく息を呑み、隣の審査員と顔を見合わせた。そして、ただ黙ってペンを走らせる音がした。
結果が発表された瞬間の喧騒は、どこか遠くに聞こえた。ふと、隣に立つ誠人と視線が合った。彼は何も言わず、ただ一度だけ、強く頷いた。その目元が少し赤く潤んでいたのを、亮介は見ないふりをした。
優勝の後、亮介は変わった。小さな店が、自分の才能に見合わない器だと感じ始めたのだ。堅実な誠人の忠告を無視し、彼はもっと大きな舞台を求めた。銀行の融資担当者と密かに会い、一等地の新しい物件の契約話を進めた。店の共同名義を使い、誠人に内緒で、一人で店の未来を決めようとしていた。自分の料理があれば、どんな借金も返せる。そう、本気で信じ込んでいた。
「……亮介、これは何だ」
亮介の鞄から見つけた融資契約書を手に、誠人の声は震えていた。
「説明するつもりだった。これはチャンスなんだ」
「俺たちの店は、ここじゃないのか」
「こんな場所で終わるつもりか? 俺たちはもっと上に行ける」
その言葉が、決定的な一言だった。誠人は、何も言わずに契約書をテーブルに置くと、静かにエプロンを外した。「お前の好きにしろ」と言い残し、彼は店を出て行った。二度と戻らなかった。
結局、亮介一人では、大きすぎた計画を動かすことなどできはしなかった。店は、彼の野心の重さに耐えきれず、静かに潰れた。
「……以上だ」
目を開けた亮介の前で、マスターは静かに頷いていた。
「なるほど。輝かしい記憶ほど、裏側の影もまた、濃くなるものですな」
その言葉は、同情とも、ただの事実の確認ともつかない響きを持っていた。
空っぽの小瓶
記憶の抽出が終わり、虹色の液体が小さな小瓶に満たされる。マスターは査定額であろう数枚の紙幣をカウンターに置いた。だが、亮介はそれに手を触れなかった。
「代金は、要らない」
彼は自分の財布からコーヒー代の千円札だけを抜き、カウンターに置いた。
「あれは、俺が持っていていい記憶じゃなかった。だから、金をもらう筋合いもない」
ただ、重荷を降ろしたかった。それだけだ。亮介は椅子から立ち上がり、振り返ることなく店を出て行った。ベルの乾いた音が、やけに虚しく響いた。
カウンターには、客の去ったカップと、代金の受け取りを拒否された記憶の小瓶、そして一枚の千円札が残された。マスターはそれを静かに片付けると、小瓶に『ビストロ・ノスタルジー、奇跡のスフレ』と記したラベルを貼り、記憶リストの末尾にその一行を書き加えた。
渇望する料理人
その日の夜、店のドアベルが再び鳴った。
入ってきたのは三十代半ばの男。目の下の隈、擦り切れたコックコートの袖口。同業者だとすぐに分かった。男はカウンターの椅子に、崩れるように座った。
「マスター……何か、ありませんか。インスピレーションになるような記憶を」
男──高田雄太は、近所で小さなビストロを営むシェフだった。客はそこそこ入っているが、自分の料理に納得がいかない。ただ、真っ白な皿を前にして、何も思いつかない時間だけが過ぎていくのだと、力なく語った。
マスターが静かに記憶のリストを差し出す。雄太は、その羊皮紙のリストを力なく眺めていたが、ある一行に目が留まった。昼間、書き加えられたばかりの一行に。
『ビストロ・ノスタルジー、奇跡のスフレ』
「……え」
雄太は顔を上げた。その目に、かすかな光が宿る。
「まさか……あの店の記憶が、なぜここに?」
彼はマスターに語り始めた。
「俺、七年前に一度だけ、あの店で食べたことがあるんです。自分の才能に絶望して、店を畳もうと思っていた日に。……なんていうか、楽しそうだったんです。作っている人が。料理が、歌っているみたいだった」
雄太は、なけなしの金を払い、その記憶を購入した。売り手がどんな人物なのか、なぜこの記憶が代金不要で売られていたのか、彼は知る由もなかった。
温かいデセール
虹色の液体が、雄太の喉へと吸い込まれていく。
長い沈黙。
記憶の旅から戻ってきた雄太は、しばらく動かなかった。やがて、その肩が小さく震え始める。
「……そうか」
ぽつりと、嗚咽混じりの声が漏れた。
「……不安だったんだな、あの人たちも。でも、楽しそうだ……」
彼は顔を上げた。目には涙が滲んでいたが、来る時のような暗い色合いはどこにもなかった。
「ソースの隠し味……カイエンペッパーだったんですね。あのピリッとした刺激が、ずっと忘れられなかった」
雄太は、マスターに向かい、深く、深く頭を下げた。
「ごちそうさまでした。俺も、自分の厨房に帰ります」
客が去り、再び静寂が戻る。マスターはカウンターを片付けると、雄太が払った記憶の代金を静かに抽斗にしまった。
夜明けのコーヒー
数日後、店のドアベルが、また鳴った。
カウンターの向こうで本を読んでいたマスターが顔を上げると、そこに立っていたのは工藤亮介だった。
「……また、ブレンドを」
席に着いた亮介は、それだけ言った。
何十年も胸につかえていた重石が取れたはずなのに、心は奇妙なほど静かだった。軽くなったというより、何か大事なものまで一緒に失くしてしまったような、漠然とした喪失感が漂っている。すっきりしない。そのモヤモヤの正体を確かめたいような気持ちに駆られ、無意識にここまで歩いてきてしまった。
コーヒーが、静かに差し出される。
「……あれから、どうにも体の調子がいい。長年の肩こりが、ようやく取れたようだ」
誰に言うでもなく、亮介は自嘲気味に呟いた。
その言葉に、マスターは初めて顔を上げた。
「そうですかな?」
彼は、磨いていたグラスを置くと、静かに続けた。
「お客様が先日、手放された『重荷』ですが、ある方がそれを求めてこられまして」
「……」
「その方も何かを背負ったご様子でしたが、お帰りの際には、とても晴れやかな顔をしておられましたよ」
亮介は、コーヒーカップを持つ手で、動きを止めた。
自分が何を売ったのか、それがどんな過去だったのか、もう永遠に思い出すことはない。ただ、胸の奥で燻っていた罪悪感だけが、確かにここへ来て消えた。
その、自分が捨てた、名前もわからないほどの過去の一部が、顔も知らない誰かの役に立った。
贖罪にもならない、ただの自己満足の逃避だと思っていた。だが、自分の人生から切り捨てた部分が、無価値なゴミではなかった。その事実が、彼の空っぽになった心に、静かで温かいものを、ゆっくりと満たしていくようだった。
「……そうか」
亮介は、ただそれだけ呟いた。
カップに残っていたコーヒーを、一気に飲み干す。不思議と、今度のそれは温かかった。
「ごちそうさん」
彼は、今度こそ本当に穏やかな顔で立ち上がると、マスターに軽く頭を下げて店を出て行った。
マスターは一人、客の去った空間で、カウンターを拭いていた。
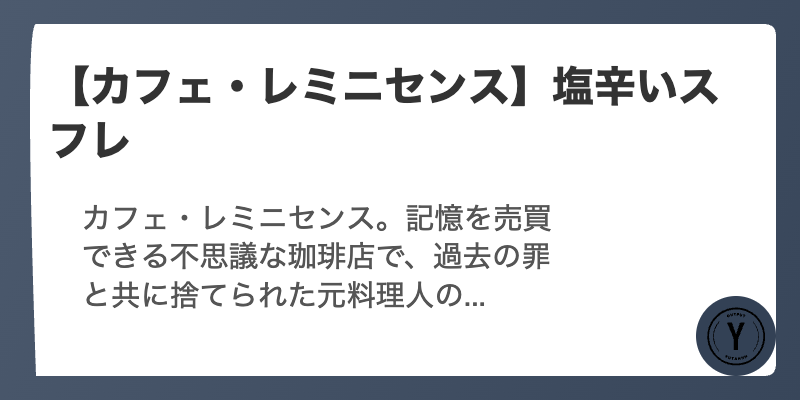
コメント