残滓(ざんし)
東京の夏は、ただ熱いだけの粘土だ。アスファルトが陽炎を揺らし、室外機の吐き出す熱風が澱んだ空気をかき混ぜる。俺の左足は、こういう湿度を帯びた熱に苛まれると、決まって鈍く疼きだす。失くしたはずのくるぶしから先が、まるで水中で膨れきったように重く、そして冷たい。健常な右足が汗ばむほど、失った左足は氷のように冷えるのだ。皮肉なものだ。
八月になると、その疼きは神経を逆撫でするような痒みへと変わる。蝉の声が、あの川の瀬音に聞こえ始める。道行く子供の甲高い声が、Aの最後の叫びと重なる。そう、全ては盆が近いせいだった。死んだ人間が、一年に一度だけ帰ってくるという、あの季節。俺の身体には、死んだはずのAの残滓が、夏の残滓が、今もなおこびりついている。
事故から、五年。いや、六年か。もう指を折って数えることもしなくなった。Aの命日も、墓参りも、いつからか避けている。彼の実家から届く、律儀な盆の知らせの葉書も、読まずに引き出しの奥へ仕舞うだけだ。罪悪感。ありふれた言葉だが、その粘着質な手触りを、俺ほど知り尽くした人間もそうはいないだろう。それはまるで、川底の泥。足を取られ、身動きを封じ、ただ沈んでいくのを待つしかない。
「……行かなければ」
誰に言うでもなく、呟いていた。エアコンの低い唸りだけが支配する、ワンルームの部屋。何故、今になって。分からない。ただ、疼く足が、痒みが、耳の奥で反響する瀬音が、俺をあの場所へ帰れと命じている。見殺しにした友の亡骸が沈む、あの淵へ。そうしなければ、この疼きも、この夏の熱も、俺の中から永遠に出ていかないような気がした。
俺は重い腰を上げ、クローゼットの奥から埃をかぶったボストンバッグを引きずり出した。それはあの日、Aと共にあの川へ向かった時に使っていたものだった。ファスナーを開ける。黴と、夏の光の匂いが、むわりと立ち上った。
白昼夢(はくちゅうむ)
あの日の空は、抜けるような青だった。絵の具を塗りたくったような、非現実的なまでの青。俺とAは、自転車を飛ばして町外れの雑木林を抜け、秘密の遊び場であるあの川を目指していた。ペダルを漕ぐ足も軽く、額の汗さえも輝かしい勲章のようだった。
「おい、競争な! 淵まで一番乗りした方が、売店のガリガリ君おごりだ!」
Aが振り返って叫ぶ。日に焼けた白い歯が、太陽の光を跳ね返した。それが、俺の見た彼の最後の笑顔だった。
淵は、俺たちの王国だった。木々の枝葉が天蓋のように覆い被さり、外界の猛烈な日差しを和らげて、水面には玉虫色の光が揺らめいていた。水はどこまでも透明で、川底の丸い石の一つ一つが、手のひらに取るように見えた。俺たちは歓声を上げ、火照った身体のまま、その冷たい水の中へ飛び込んだ。肌を刺すような水の冷たさが、すぐに官能的な快感へと変わる。Aと二人、飽きもせずに潜り、泳ぎ、水をかけ合った。世界は完璧で、永遠にこの夏が続くのだと、本気で信じていた。
変化は、唐突に訪れた。
あれほど青く澄んでいた空に、どこからか鉛色の雲が湧き出し、あっという間に太陽を覆い隠したのだ。木々のざわめきが止む。鳥の声も、虫の音も、ぴたりと消えた。さっきまでの喧騒が嘘のような、不気味な静寂。そして、ぽつり、と大粒の雨が水面に円を描いた。
「夕立かな。帰るか」
俺が岸へ向かおうとした、その時だった。ごう、という地鳴りのような音と共に、上流から濁流が押し寄せてきたのは。穏やかだった清流が、一瞬で牙を剥いた。茶色く濁った水が渦を巻き、俺たちの身体を容赦なく弄ぶ。
「助け……!」
Aの声。すぐ近くにいたはずなのに、濁った水の中では彼の姿を捉えられない。俺は必死に手を伸ばした。その指先に、確かにAの腕が触れた。掴もうとした、その瞬間。足元の岩に左足を強かに打ち付け、激痛と共に意識が遠のいていく。俺の手から、Aの感触がするりと抜けていった。最後に聞こえたのは、ごぼり、という水の音だけ。
それが、俺の白昼夢。盆の時期にだけ見る、鮮明すぎる悪夢の正体。
呼び声(よびごえ)
数年ぶりに降り立った故郷の駅は、記憶の中よりずっと寂れていた。バスに揺られ、かつての遊び場へと向かう。かつては子供たちの声で満ちていたはずの川辺は、今は立ち入り禁止の看板が立つばかりで、人の気配はまるでない。
淵。
そこだけが、時が止まったかのように昔のままだった。木々の天蓋も、水の透明度も。ただ、そこにAはいない。俺の足も、もうあの頃のようには動かない。杖を頼りに、ゆっくりと水際まで歩を進める。
ざあ、と風が木々を揺らす。葉擦れの音に混じって、何かが聞こえた気がした。
「……い……で」
幻聴だ。分かっている。医者にもそう言われた。強すぎる罪悪感が見せる、ただの幻。俺は首を振って、その声を打ち消そうとする。
不自由な足を、そっと淵の水に浸した。あの日と同じ、肌を刺すような冷たさ。だが、すぐに慣れた。むしろ、疼く古傷の熱を、この水が吸い取ってくれるような心地よささえある。俺は杖を傍らに置き、浅瀬に腰を下ろした。
「お……いで……」
まただ。今度は、もっとはっきりと聞こえた。Aの声だ。間違いなく。
「こっちの……水は……つめたくて……きもちいいぞ……」
心臓が、鷲掴みにされたように軋む。幻聴だ。そう自分に言い聞かせても、声は水面を渡って、確かに俺の耳に届く。
「A……」
思わず、彼の名を呼んだ。馬鹿なことを。死んだ人間が、いるはずがない。
その時だった。腰まで浸かっていた身体の、その足首に、何かがぬるりと絡みついた。驚いて水の中を見る。川藻だ。長く伸びた川藻が、俺の足にまとわりついているだけ。そう思った。
だが、藻はまるで指のように、五本、俺の足首を掴んで離さない。そして、ゆっくりと、しかし抗いがたい力で、淵の中心へと引いていくのだ。
「う、わっ……!」
慌てて岸へ戻ろうとするが、足が動かない。川の流れが、まるで生きた腕のように俺の身体を捉えている。
「おいで……ひとりは……さみしいんだ……」
声は、すぐ水面の下から聞こえる。もう、幻聴だとは思えなかった。恐怖で全身の毛が総毛立つ。だが、同時に、奇妙な安堵感が胸に広がっていくのを、俺は感じていた。ああ、これで楽になれる。Aのもとへ行ける。罪を、償える。身体から力が抜けていく。死という名の甘美な陶酔が、俺を淵の底へと誘っていた。
淵と共に
引きずり込まれる。
身体が、ゆっくりと深みへ傾いでいく。水が耳に入り込み、世界から音が消える。見えるのは、水を通して歪んだ木々の緑と、鉛色の空だけ。意識が朦朧とする中、俺は水底を見た。
そこには、誰もいなかった。
あるのは、揺らめく川藻と、光を反射してきらめく丸い石だけ。Aの姿も、俺の足を掴む腕も、どこにもない。
――なんだ。
――やっぱり、全部、幻だったのか。
俺の罪悪感が、この淵にAの姿を、彼の声を、そして彼の手を創り出していただけだったのか。
そう悟った瞬間、足首に絡みついていたはずの力が、ふっと消えた。
ぷは、と俺は水面に顔を出す。大きく息を吸い込むと、肺に新鮮な空気が流れ込み、激しく咳き込んだ。冷たい水の中で、身体はがたがたと震えている。だが、あれほど疼いていた左足の痛みは、嘘のように消え去っていた。
俺は、生きていた。
立ち上がり、岸へと向かう。もう、背後から呼び止める声はしない。川の流れも、ただの水の動きに戻っていた。
俺は淵から上がると、一度だけ、静かな水面を振り返った。
Aは、ここにはいない。
最初から、どこにもいなかったのだ。いたのは、友を見殺しにした罪悪感から逃げ続けた、弱い俺の心だけ。
だが、本当にそうだろうか。
あの声は。あの腕の感触は。本当に、全てが俺の創り出した幻だったと、言い切れるのか。
分からない。
もう、確かめようもない。
俺は濡れた身体のまま、杖を拾い、ゆっくりと歩き出した。淵を背にして。
もう、二度とここへは来ないだろう。
だが、分かっている。これから先も、盆が来るたびに俺は思い出すのだ。あの淵の、肌を刺す水の冷たさを。そして、水底へと誘う、甘い呼び声を。
その声が幻聴であったとしても、それは俺という人間の一部なのだ。淵は、もう俺の中に在る。俺は、あの淵と共に、生きていくしかない。
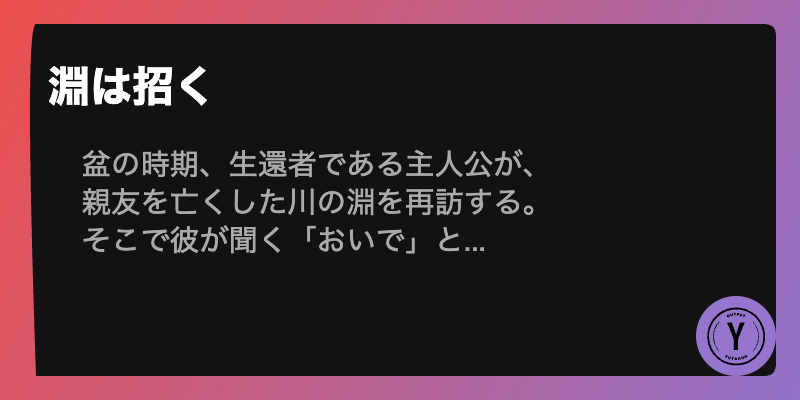
コメント