宵宮(よいみや)
相葉健太は、人いきれと甘いソースの匂いが混じり合う、その祭りの空気をどこか懐かしく感じていた。グラフィックデザインの仕事でこの田舎町に仮住まいを始めて一月。都会の無機質な喧騒に慣れた耳には、祭囃子のどこか間延びした音階が、かえって新鮮に響く。健太自身、こういう人混みは好む方ではなかった。幼い頃から、人と同じものが見えているという確信が持てなかったからだ。人の多い場所では、時折、そこにいるはずのないものの輪郭が、陽炎のように視界の端をちらつく。そのたびに、自分だけがこの世界から一枚隔てられた場所にいるような、薄ら寒い孤独を覚えるのだ。
「兄ちゃん、りんご飴いるかい?」
夜店の威勢のいい声に、健太は曖昧に笑って首を振った。白熱電球が照らす橙色の光は、人々の顔に温かな陰影を落とし、誰もが幸福そうに見える。子供たちは目を輝かせ、若者たちははにかみながら肩を寄せ合う。健太はカメラを片手に、その温かな光景をファインダーに収めていた。仕事の資料集め、というのは建前で、本当は少しだけ、この町の息遣いに触れてみたかったのかもしれない。
神社の境内は、本殿へ向かう参道が一番の賑わいを見せていた。健太は人の波を避けるように、少し寂れた脇道へ逸れる。古びた末社が並び、その裏手には小さな森が夜の闇を深く湛えている。喧騒が嘘のように遠のき、ひんやりとした空気が肌を撫でた。
その時だった。
くす、としゃくりあげるような、小さな音が耳に届いたのは。
音のする方へ視線を向ける。末社の、提灯の光も届かない一番奥の暗がり。そこに、小さな人影がうずくまっていた。
おかっぱ頭に、金魚の柄が染め抜かれた、少し色褪せた浴衣。年の頃は、五つか六つくらいだろうか。少年は両手で顔を覆い、声を殺して泣いていた。
「どうしたんだい? 迷子かな」
健太は、なるべく優しい声で話しかけた。少年はぴくりと肩を揺らしたが、顔を上げようとはしない。その小さな背中が、絶望に打ちひしがれているように見えた。健太は周りを見渡すが、親らしき人物は見当たらない。不思議なことに、時折この脇道を通る人々も、泣いている少年に一瞥もくれず通り過ぎていく。まるで、そこに少年など存在しないかのように。
まただ、と健太は思った。胸の奥が、すうっと冷たくなる。これは、いつもの「あれ」だ。見えてはいけないものを、自分だけが見てしまっている。
健太は、少年にかける言葉を失った。ただ、賑やかな祭囃子の音だけが、遠くで鳴り響いていた。
はぐれ鴉(からす)
正一は、母ちゃんの大きな手のひらの温かさを、確かに感じていた。
「しょうちゃん、絶対に手を離したらあかんで」
そう言う母ちゃんの声は、周りのざわめきで少し遠くに聞こえた。生まれて初めて見る、夜の夏祭り。空はまだ藍色で、神社の入り口では、火の玉みたいな裸電球がたくさん灯っていた。正一は、人の足の林をかき分けるようにして、母ちゃんの後をついて歩いた。
甘い匂いがした。見ると、白い雲みたいな砂糖菓子を、おじさんが棒に巻き付けている。綿飴、というらしい。
「母ちゃん、あれほしい」
「こら、わがまま言うたらあかん。帰りに買うてあげるから」
正一は少し口を尖らせたが、すぐに新しいものに心を奪われた。ぱん、ぱん、と乾いた音がする方では、お兄さんたちが鉄砲で何かを狙っている。景品のブリキのロボットが、正一をじっと見ていた。
その時だった。
わあっ、という大きな歓声が上がり、人の波が大きく揺れた。誰かが正一の身体にぶつかり、よろけた拍子に、繋いでいた母ちゃんの手が、するりと抜けてしまったのだ。
「あ……」
一瞬のことだった。気づいた時には、母ちゃんの浴衣の裾は、もう見えなくなっていた。
「母ちゃん!」
叫んだ声は、人の波に掻き消される。周りにあるのは、知らない大人の膝と、足、足、足。みんな空の上のほうを見て笑っていて、誰も足元で途方に暮れている正一のことなど、見ていなかった。
焦りと不安で、心臓がどきどきと速くなる。泣いちゃだめだ。泣いたら、母ちゃんに見つけてもらえない。正一は必死で涙をこらえ、人の流れに逆らって歩き始めた。母ちゃんを探さないと。
でも、どこへ行けばいいのか分からない。境内は迷路みたいに広くて、どこもかしこも同じような提灯がぶら下がっているだけ。
「かあ……ちゃん……」
とうとう、堪えきれずに涙がぽろりと零れた。心細さで、足が動かなくなる。正一は、少しでも人のいない場所へ行こうと、明るい参道から外れ、暗い神社の裏手へとふらふら迷い込んでいった。そこにいれば、いつか母ちゃんが探しに来てくれるかもしれない。
正一は、一番奥の暗がりで、膝を抱えてうずくまった。ひっく、ひっくと、しゃくりあげる声だけが、暗闇に吸い込まれていった。
影法師
祭りの夜から三日経っても、健太の頭からはあの少年の姿が離れなかった。あの後、健太がもう一度振り返った時、そこにはもう誰の姿もなかったのだ。
仕事も手につかず、健太は町の小さな資料館に足を運んでいた。古い民家を改装しただけの、黴と墨の匂いがする場所。受付にいた老婆に会釈し、郷土史の棚を漫然と眺める。何か、手がかりはないか。
「何か、お探しかね」
不意に背後から声をかけられ、健太は飛び上がるほど驚いた。受付にいた、腰の曲がった老婆だった。
「あ、いえ……この町の、昔の夏祭りのこととか……」
「ほう、祭りに。よそから来た人かい」
健太が頷くと、老婆は皺くちゃの顔を綻ばせた。「それなら、面白い話がある」と言って、古いアルバムを奥から持ち出してきた。
「この神社の神様は寂しがり屋でな。祭りの晩、気に入った子供を遊び相手に欲しがるんじゃ。呼ばれた子は、社の周りから出られなくなる。周りには大勢人がいるのに、誰にも姿が見えず、声も届かなくなる。そうして神様の遊び相手を務めて、朝になると、鳥居の外にぽつんと戻される。中の記憶は、すっかりなくなっとるがのう」
老婆は、淡々とした、抑揚のない声で語る。
「じゃが、ごく稀に、神様がたいそう気に入ってしまって、朝になっても返してくれん子がおる。それが本当の『神隠し』じゃよ」
「わしが子供の頃にも、一人おった。正一ちゃん、いうてな。おかっぱ頭の、可愛らしい子じゃったが……祭りの晩に、母親の手を離して、それっきり」
健太の心臓が、冷たい手で掴まれたように痛んだ。
老婆は、健太の反応など意に介さず、古い新聞の切り抜きが挟まったページを開いた。
『昭和三十八年八月十五日、夏祭りにて男児行方不明』
その見出しの下に、色褪せた一枚の写真。金魚柄の浴衣を着て、はにかむようにおかっぱ頭を傾けている、幼い少年。
――正一。
「その子が最後に目撃されたのが、神社の裏にある末社のあたりじゃったそうじゃ」
老婆の声が、ひどく遠くに聞こえる。
「今でも、盆の時期の祭りの晩になると、出るそうだよ。母親を探して泣く、正一ちゃんの声がな。もっとも、見えるのは、わしらみたいな年寄りか、あんたみたいな『呼ばれた』人だけらしいがね」
資料館を出た時、空はどんよりとした曇り空だった。
温かい人情の町。賑やかな夏祭り。その全てが、色褪せたフィルムのように見えた。健太は、あの少年の正体を知ってしまった。彼が昭和の時代からずっと、たった一人で、あの暗がりで泣き続けているという事実を。
それは、同情や哀れみといった感傷を、一瞬で凍らせるほどに、冷たくて、どうしようもない事実だった。
祭りのあと
――昭和三十八年。正一は、見えない壁にぶつかっていた。
神社の裏手から賑やかな参道へ戻ろうとすると、まるで分厚いガラスがあるみたいに、どうしても先に進めないのだ。すぐそこに母の姿が見えるのに、どんなに叫んでも声は届かず、誰も正一に気づかない。祖母から聞かされた古い話を思い出す。『祭りの晩、神様に気に入られた子は、隠されてしまうんよ』。それが今、自分の身に起きているのだと悟った時、子供の心を絶望的な恐怖が塗り潰した。
その時だった。空が鳴り、今までのが嘘のように、激しい夕立が降り始めたのは。
見えない牢獄の中で、正一は容赦なく雨に打たれる。逃げ場はない。濡れた浴衣が肌に張りつき、体温をごっそりと奪っていく。寒さと恐怖で身体の震えが止まらない。ひゅっ、と喉が鳴り、息が苦しくなってくる。
母ちゃん。助けて。
そう心で叫んだのを最後に、彼の小さな魂は、神様の境内から、二度と出られなくなった。
――現在。
来週末、健太はこの町を去る。プロジェクトが終わり、東京へ帰るのだ。
去る前に、もう一度だけ、あの祭りの夜がやってきた。健太は迷った末、カメラも持たずに家を出た。足は、自然とあの神社へ向かっていた。
境内は、先週と同じ賑わい。同じ祭囃子。同じ人々の笑顔。
健太は、脇目も振らずに神社の裏手へ向かう。
いた。
末社の暗がり。色褪せた金魚柄の浴衣。おかっぱ頭。
少年は、先週と全く同じ姿で、声を殺して泣いていた。
健太は、もう彼に声をかけなかった。声をかけても届かない。手を伸ばしても、触れることすらできない。彼は、この賑やかな世界から、完全に断絶された影法師なのだ。健太にできることは何もない。慰めることも、手を引いてやることも、母親の元へ連れて行ってやることも。
健-太にできるのは、ただ、そこにいることだけ。
彼の途方もない孤独を、どうしようもない哀しみを、「知っている」人間が、今この瞬間、ここに一人だけいると、ただ知らせてやることだけ。
健太は、少年のそばに、ただ黙って立った。
どれくらいの時間が経っただろうか。不意に、少年のしゃくりあげる声が、ほんの少しだけ、小さくなったような気がした。
健太は、少年に背を向け、ゆっくりと歩き出した。
賑やかな参道へ戻る。人々の波に身体を預ける。もう、振り返らない。
この町を去っても、健太は決して忘れないだろう。この温かい光に満ちた世界の、ほんの片隅にある小さな暗がりを。そして、そこで永遠に親を探し続ける、幼い魂の存在を。
見えてしまう自分の体質を、彼はこれからも呪い続けるのかもしれない。
だが、あの夜、あの瞬間のことだけは。
健太は、見えてよかったと、そう、心のどこかで思っていた。
祭囃子が遠のいていく。まるで、一つの夏が終わるように。
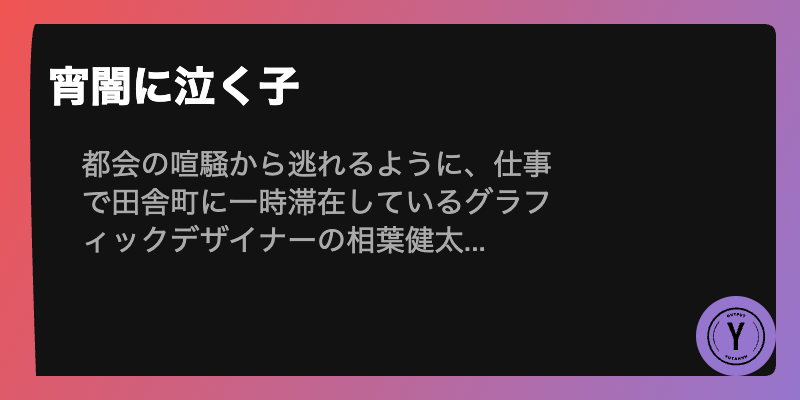
コメント